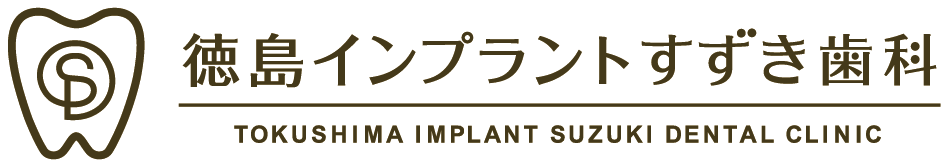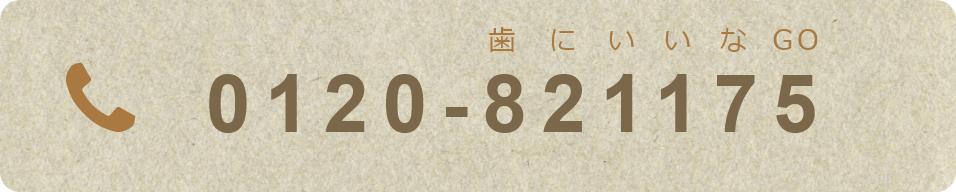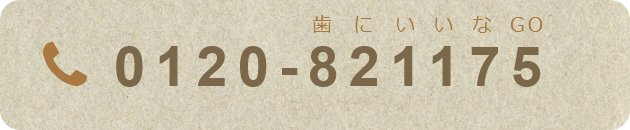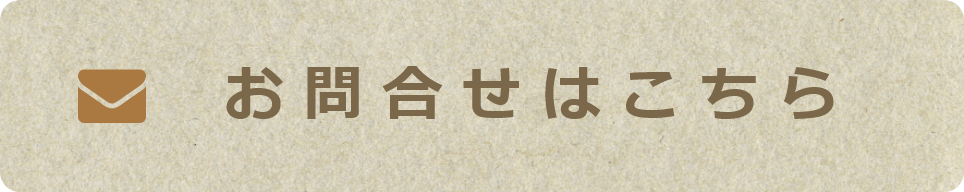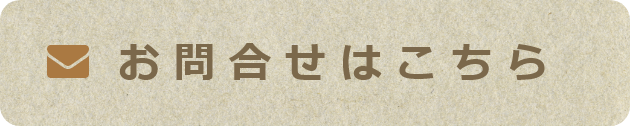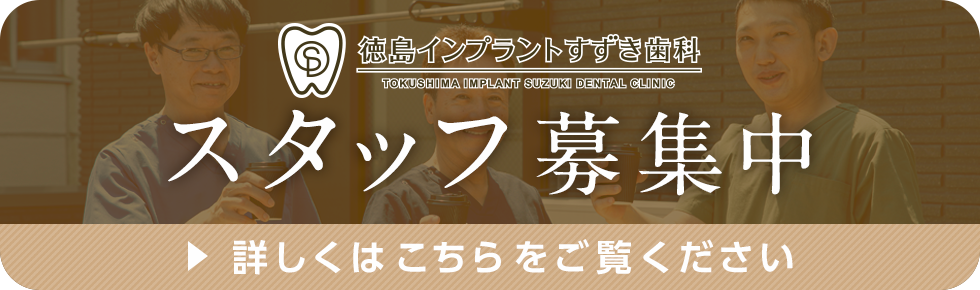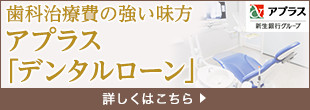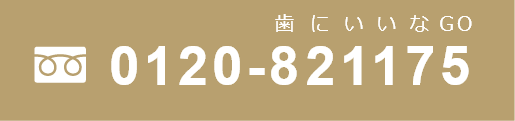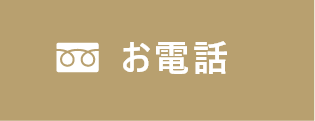- HOME
- 医院ブログ
歯を失う原因は虫歯よりも歯周病?
2025.09.10
はじめに
「歯が抜ける一番の原因は虫歯ではない」という事実をご存じでしょうか?
実は、大人が歯を失う原因として最も多いのは“歯周病”であり、子どもの頃から虫歯予防にしっかり取り組んできた方でも、歯周病についてはあまり意識してこなかったという方が少なくありません。
厚生労働省の調査によると、40歳以上の日本人の約8割が歯周病にかかっているとされており、年齢を重ねるにつれて、歯周病によって歯を失う人の割合が増加していくという現状があります。
今回は、虫歯と歯周病の違い、歯を失う原因、予防のポイントをわかりやすくまとめました。
虫歯と歯周病の違いについて
「虫歯」と「歯周病」は、どちらも私たちの口の中で起こる非常に身近な病気であり、どちらも放置すれば歯を失う可能性がある点では共通していますが、発生のメカニズムや症状の現れ方、進行の仕方、治療方法、そして予防法などが大きく異なることをご存じでしょうか。
まず、虫歯(正式には「う蝕」)とは、口腔内に存在する細菌、特に「ミュータンス菌」と呼ばれる細菌が、飲食物に含まれる糖分をエサとして酸を作り出し、その酸によって歯の表面を覆っている硬いエナメル質や、その内側にある象牙質を少しずつ溶かしていく病気です。
虫歯の進行は、一般的に歯の表面から内側に向かって段階的に進み、進行すると歯の神経にまで達して強い痛みを引き起こすようになります。初期の虫歯では自覚症状が少ないものの、進行するにつれて冷たいものや甘いものがしみるようになったり、ズキズキとした自発痛が現れたりと、比較的早い段階で何らかの異変に気づきやすいという特徴があります。
一方で、歯周病は、歯そのものではなく、歯を支えているまわりの組織、つまり歯ぐき(歯肉)や歯根膜、歯槽骨などが細菌によって徐々に破壊されていく病気です。
原因となるのは、歯と歯ぐきの境目にたまったプラーク(歯垢)であり、この中に含まれる歯周病菌(代表的なものにポルフィロモナス・ジンジバリスなど)が歯ぐきに炎症を引き起こし、やがて歯槽骨を溶かしながら進行していきます。
歯周病の怖いところは、進行していても痛みがほとんどないため、自覚症状がないまま静かに、しかし確実に歯の支えを奪っていく点です。このため、「サイレントディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれ、気づいたときには歯がグラグラしていたり、最悪の場合、自然に抜け落ちてしまうケースもあります。
虫歯は一本の歯ごとに発生することが多く、局所的な問題であるのに対し、歯周病はお口全体に広がりやすく、複数の歯が同時に影響を受けやすいという性質があります。
また、虫歯によって失われた歯質は人工材料で補うことができる一方で、歯周病で失われた歯槽骨は、通常の治療だけで元に戻すことは非常に難しいという違いもあります。
さらに、虫歯は主に「糖分の摂取」や「歯磨き不足」によってリスクが高まるのに対し、歯周病は「歯垢の蓄積」だけでなく、「加齢」「喫煙」「ストレス」「全身疾患(特に糖尿病)」など、より多くの生活習慣や体の状態と関係しています。
このように、虫歯と歯周病はどちらも予防と早期発見が重要である点に変わりはありませんが、それぞれに異なるリスク要因があり、治療のアプローチも大きく異なるため、正しい知識を持って、日頃からのセルフケアと定期的な歯科検診の両方を継続することが、歯の健康を守るうえで非常に重要です。
※歯周病は痛みが出にくく、気づきにくい「静かな病気」です。
年齢と歯を失う原因の関係
歯を失う主な原因は、年齢とともに大きく変化します。
一般的に、若い年代では「虫歯」による歯の喪失が多く見られますが、中年以降、特に40歳を過ぎた頃からは「歯周病」が歯を失う最大の原因として浮上してきます。年齢を重ねるごとに、口腔内環境や体の免疫機能が変化し、それが歯の健康に大きな影響を与えているのです。
子どもから若い成人の間では、虫歯による歯のダメージが比較的多く見られます。これは、甘いものを多く摂取しやすい生活習慣や、まだ十分に身についていない歯磨き習慣などが関係しています。
虫歯は比較的急速に進行するため、放置すると短期間で歯の神経を侵し、抜歯に至ることもあります。しかし、この年代では歯ぐきや歯を支える骨がまだ健康なことが多く、歯周病による歯の喪失はあまり多くはありません。
ところが、30代後半から40代にかけて徐々に状況は変わっていきます。日本の厚生労働省による調査では、40歳以上の日本人の約80%が何らかの歯周病にかかっているとされています。
この頃から、歯ぐきの腫れや出血、口臭、歯のぐらつきといった症状が現れはじめ、知らず知らずのうちに歯周組織が破壊されていくケースが増えてきます。歯周病の進行は緩やかであるため、自覚症状が出にくく、気がついたときにはすでに重症化しているということも少なくありません。
50代・60代に入ると、歯周病による歯の喪失がさらに顕著になります。
この年代では、加齢による免疫力の低下や唾液の分泌量の減少、全身疾患(糖尿病や高血圧など)の影響、薬の副作用、喫煙歴などが複合的に絡み合い、歯周病がより進行しやすい環境が整ってしまいます。
また、歯周病で一度失った歯槽骨は自然には再生せず、噛む力が弱くなったり、残った歯に過度な負担がかかることで、次々と他の歯も失われる「負の連鎖」が起きてしまうこともあります。
一方で、高齢になっても歯を多く残している人もいます。そうした方々に共通しているのは、若い頃からの丁寧なセルフケアと、歯科医院での定期的なメンテナンスを習慣にしてきたという点です。
年齢によって歯を失いやすくなるのは事実ですが、それを完全に運命として受け入れる必要はなく、正しい知識と予防行動によって、歯の寿命を大きく延ばすことができるのです。
つまり、歯を失う原因には年齢による傾向があり、若年期では虫歯が、そして中高年以降では歯周病が中心となるという大きな流れがあります。これを理解したうえで、年齢に応じた予防・治療・メンテナンスを行っていくことが、健康な歯を一生保つための鍵となるのです。
生活習慣の中での歯周病予防
歯周病は生活習慣と深く関わっており、日々の習慣を少し見直すだけでも、予防や進行の抑制に大きな効果が期待できます。
歯科医院での定期的なメンテナンスはもちろん大切ですが、自宅でのセルフケアや日常生活の過ごし方が、歯周病予防の土台になります。
ここでは、生活習慣の中で実践できる具体的な歯周病予防のポイントをご紹介します。
まず第一に、正しい歯磨きの習慣が基本となります。歯周病は歯と歯ぐきの境目にたまったプラーク(歯垢)中の細菌が原因となって進行します。そのため、毎日の歯磨きでプラークをしっかり取り除くことがとても重要です。
特に歯ぐきのラインや歯と歯の間など、磨き残しが起きやすい部分に注意して、丁寧に磨くように心がけましょう。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助用具も併用することで、より効果的に清掃できます。
次に、規則正しい食生活も歯周病予防に大きな影響を与えます。糖分の多い食事や間食が多いと、口の中に細菌が増えやすくなり、プラークの形成を助長してしまいます。
また、よく噛まずに早食いする習慣も唾液の分泌が不十分になり、口腔内の自浄作用が低下してしまいます。よく噛んで食べること、バランスの良い栄養を心がけることは、歯や歯ぐきの健康を保つうえで非常に効果的です。
特に、ビタミンCやカルシウム、たんぱく質などを意識的に摂取することで、歯ぐきや骨の健康維持につながります。
また、禁煙は歯周病予防において非常に重要なポイントです。
タバコに含まれるニコチンやタールは血流を悪化させ、歯ぐきへの酸素や栄養の供給を妨げます。さらに、免疫力が低下し、歯周病菌に対する抵抗力が弱くなってしまいます。
喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病のリスクが2倍以上高いという研究結果もあります。すでに歯周病になっている場合、喫煙していると治療効果も現れにくく、回復も遅れがちです。
さらに、ストレスの管理も意外に見落とされがちな要素ですが、非常に大切です。
過剰なストレスは自律神経やホルモンバランスを崩し、免疫機能を低下させることが知られています。その結果、歯周病菌に対する抵抗力が弱まり、炎症が広がりやすくなるのです。
自分なりのリラックス法や趣味、十分な睡眠をとることでストレスを軽減し、体全体の健康を保つことが、結果として歯ぐきの健康にもつながります。
最後に、定期的な歯科受診を生活の一部に組み込むことも忘れてはいけません。
どれだけ丁寧にセルフケアをしていても、完全にプラークや歯石を除去することは難しいため、歯科医院での専門的なクリーニングや歯周ポケットのチェックを受けることが、早期発見・早期治療につながります。
最低でも半年に一度は歯科医院でのチェックを受けることをおすすめします。
投稿者: