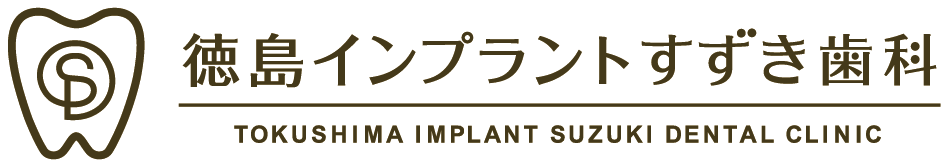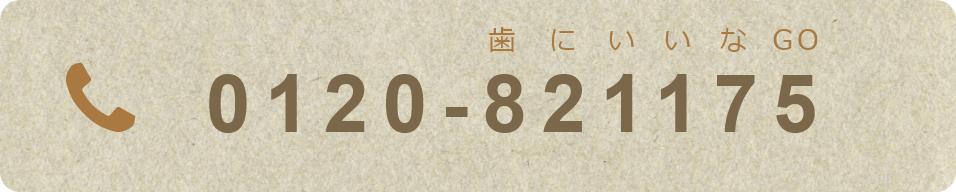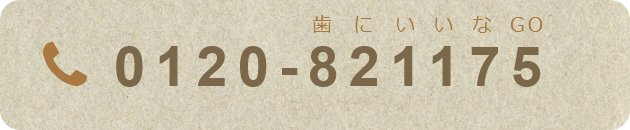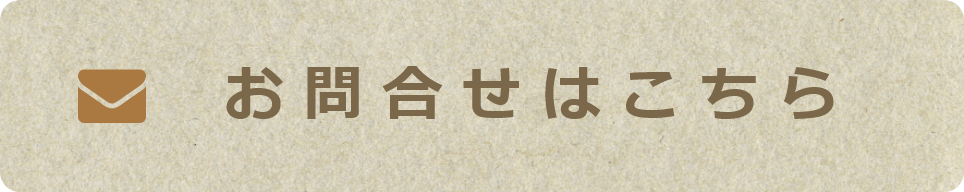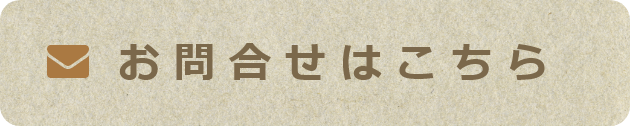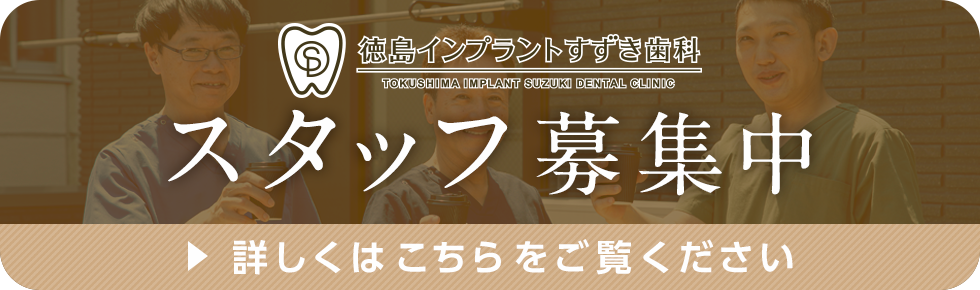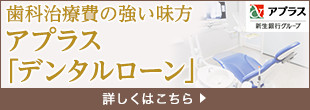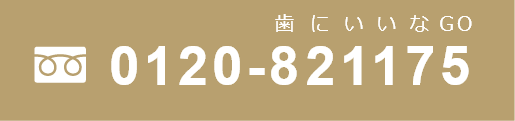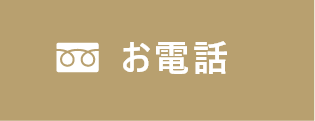- HOME
- 医院ブログ
赤ちゃん・子供の歯医者、いつから通うべき?疑問を解決する年齢別解説
2025.10.05
「赤ちゃんや子供はいつから歯医者に通うべき?」そんなママ・パパの疑問にお答えします。
結論として、乳歯が1本でも生えたら初診のタイミングです。今回は、0歳から小学生までの年齢別に、歯医者デビューの目安、定期健診の重要性、フッ素塗布やシーラントといった効果的な虫歯予防策を解説します。
さらに、歯医者さんの選び方や泣いてしまう子への対策、家庭でできる仕上げ磨きのコツまで、お子様の歯の健康を守るために必要な内容をお伝えします!
お子様の健やかな成長のために、今日からできる歯のケアを始めましょう。
目次
1.赤ちゃんや子供の歯医者デビューはいつから?
乳歯が生えたら、歯医者さんに受診することをおすすめします!
「赤ちゃんや子供の歯医者デビューはいつから?」という疑問をお持ちのママへ。結論からお伝えすると、乳歯が1本でも生えたら、できるだけ早く歯医者を受診することをおすすめします。これは虫歯になってから治療するためではなく、虫歯を未然に防ぎ、お子さんの歯と口の健康を守るための予防歯科が目的です。
お子さんの歯の健康を守る上で特に重要なポイントは以下の3つです。
|
重要ポイント |
具体的な内容 |
受診の目安 |
|---|---|---|
|
初診のタイミング |
乳歯が生え始めたら、口腔ケアの指導や虫歯リスクの評価のために受診 |
乳歯が1本でも生えたら(生後6ヶ月頃~) |
|
健診の活用 |
1歳6か月健診と3歳児健診は、歯科医師による専門的なチェックとアドバイスを受ける貴重な機会 |
1歳6か月健診、3歳児健診 |
|
定期健診の習慣化 |
虫歯予防、フッ素塗布、正しいブラッシング指導のために、定期的な通院を習慣にする |
3~6か月に一度(大人の方も対象です) |
虫歯は一度できると自然には治りません。小さいうちから予防を習慣化することで、お子さんの将来の口腔内の健康を大きく左右します。
ぜひ、この機会に「かかりつけ歯科医」を見つけ、お子さんの歯の健康を守りましょう。
1.1 初診の目安 乳歯が一本でも生えたら
赤ちゃん・子どもの歯医者デビューは、最初の乳歯が1本でも生えた時が理想的なタイミングです。多くの赤ちゃんは生後6ヶ月頃から下の前歯が生え始めます。この時期はまだ虫歯にはなりにくいと思われがちですが、実は歯が生えた瞬間から虫歯のリスクは存在します。
初診の目的は、虫歯の治療ではありません。主に以下の点について、歯科医師や歯科衛生士から専門的なアドバイスを受けることです。
・お子さんの口腔内の状態の確認
・親御さんへの正しい歯みがき方法(特に仕上げみがき)の指導
・フッ素塗布などの予防処置の検討
乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄く、虫歯の進行が非常に速い特徴があります。早めに歯医者を受診し、予防の知識と習慣を身につけることが、お子さんの大切な乳歯を守る第一歩となります。
1.2 「1歳6か月健診」と「3歳児健診」を活用
自治体が行う1歳6か月児健診と3歳児健診は、お子さんの成長発達を総合的に確認する大切な機会であり、歯科健診もその重要な一部です。これらの健診では、歯科医師や歯科衛生士が、お子さんの口腔内の状態を専門的にチェックしてくれます。
虫歯の早期発見・早期治療につながるだけでなく、今後の口腔ケアの方針を立てる上でも非常に役立ちます。健診をきっかけに、かかりつけの歯科医院を見つけ、定期的な通院へとつなげていくことをおすすめします。
1.3 定期健診を習慣化するタイミング
歯の健康を長期的に守るためには、虫歯になってから歯医者に行くのではなく、定期的な健診を習慣化することが最も重要です。理想的な通院頻度は、お子さんの虫歯リスクや口腔内の状態にもよりますが、一般的には3か月から6か月に一度の受診が推奨されます。
定期健診では、主に以下のような予防処置や指導が行われます。
・歯のクリーニング(歯垢や歯石の除去
・フッ素塗布による歯質の強化
・虫歯のチェックと早期発見
・歯並びや噛み合わせの成長観察
1歳6か月健診や3歳児健診を終えた後が、この定期健診を習慣化する良いタイミングです。継続的な予防ケアにより、お子さんが大人になっても健康な歯を保つための土台を築くことができます。
2.年齢別の通院ガイド
お子さんの成長段階に合わせて、適切な口腔ケアと歯科受診のタイミングは異なります。ここでは、年齢ごとの具体的なケア方法と、歯医者さんで受けられる予防処置について詳しく解説します。
2.1-1 0歳から1歳前の赤ちゃんの口腔ケア
この時期は、乳歯が生え始める大切な準備期間です。まだ歯が生えていなくても、口腔ケアを始めることで、お子さんが将来の歯みがきに慣れるきっかけを作ることができます。
2.1-2 口腔ケアの始め方とガーゼ磨き
歯が生える前から、清潔なガーゼを指に巻き、お口の中を優しく拭いてあげることから始めましょう。これにより、お口に触られることに慣れさせ、口腔内の清潔を保つ習慣を身につけさせることができます。
乳歯が1本でも生え始めたら、いよいよ本格的な口腔ケアのスタートです。最初はガーゼや専用の乳児用歯ブラシ(ヘッドが小さく、毛が柔らかいもの)を使い、優しく歯を拭くように磨いてあげましょう。特に寝る前のケアは重要です。
|
月齢の目安 |
口腔ケアのポイント |
歯科受診の目安 |
|---|---|---|
|
生後0~5ヶ月 |
授乳後などに清潔なガーゼで歯ぐきや舌を優しく拭く |
特に問題がなければ、乳歯が生え始めた頃 |
|
生後6ヶ月~1歳前 |
乳歯が1本でも生えたら、ベビー用歯ブラシやガーゼで優しく磨く |
乳歯が1本生えたら、遅くとも1歳までには初診を検討 |
2.1-3 授乳・哺乳瓶と虫歯リスク
母乳やミルクは、お子さんの成長に不可欠ですが、長時間お口の中に残ると虫歯のリスクを高めることがあります。特に、寝かしつけの際に哺乳瓶をくわえさせたまま寝てしまったり、だらだらと授乳・哺乳を続けたりする習慣は「哺乳瓶う蝕」の原因となる可能性があります。授乳後や哺乳瓶を使用した後は、ガーゼで優しく拭いてあげたりすることが大切です。
2.2-1 1歳から2歳の口腔ケア
この時期には多くの乳歯が生え揃い始め、お子さん自身も歯ブラシに興味を持ち始める頃です。親による仕上げ磨きが最も重要になる時期でもあります。
お子さんが自分で歯ブラシを持ちたがるようになったら、「自分で磨く」練習を始めさせてあげましょう。ただし、この時期のお子さんにはまだ十分な歯みがきスキルはありません。そのため、保護者による丁寧な仕上げ磨きが不可欠です。
仕上げ磨きは、奥歯の溝や歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目など、虫歯になりやすい部分を意識して行いましょう。お子さんを寝かせたり、膝の上に抱えたりして、お口の中がよく見える体勢で行うと効果的です。嫌がるときは、歌を歌ったり、鏡を見せたりして、楽しい雰囲気を作る工夫も大切です。
2.2-2 フッ素配合歯磨き粉の選び方
フッ素は、歯の質を強くし、虫歯菌の活動を抑える効果があります。1歳を過ぎたら、フッ素配合の歯磨き粉の使用を検討しましょう。
お子さん用のフッ素配合歯磨き粉を選ぶ際は、以下の点に注意してください。
・フッ素濃度:日本小児歯科学会では、6ヶ月から2歳にはフッ素濃度950ppm、3歳から5歳にはフッ素濃度950ppm、6歳以上にはフッ素濃度1000~1500ppmの歯磨き粉を推奨しています。お子さんの年齢に合った濃度を選びましょう。
・使用量:1歳から2歳のお子さんには、ごく少量(切った爪の先程度、または米粒大)で十分です。
・うがい:うがいがまだできないお子さんには、泡立ちが少なく、飲み込んでも安全な量のフッ素配合歯磨き粉を選び、磨いた後に濡らしたガーゼで拭き取る方法も有効です。
不明な点があれば、かかりつけの歯科医師や歯科衛生士に相談して、お子さんに合った歯磨き粉を選びましょう。
2.2-3 3歳から6歳の口腔ケア
この時期は、乳歯がすべて生え揃い、永久歯への生え替わりに備える大切な時期です。予防処置を積極的に取り入れ、虫歯になりにくい口腔環境を整えましょう。
2.2-4 フッ素塗布・シーラントの予防
歯科医院での高濃度フッ素塗布は、虫歯予防に非常に効果的です。フッ素を歯に直接塗布することで、歯の表面を強化し、酸への抵抗力を高めます。定期的なフッ素塗布は、乳歯だけでなく、これから生えてくる永久歯の虫歯予防にもつながります。
また、奥歯の溝は深く複雑な形をしており、歯ブラシが届きにくいため、虫歯になりやすい場所です。この溝を歯科用のプラスチックで埋める「シーラント」という予防処置も有効です。特に、6歳臼歯と呼ばれる最初の永久歯が生えてくる時期に検討すると良いでしょう。
2.2-5 食習慣とおやつの工夫
3歳を過ぎると、お子さんの食生活も多様になります。規則正しい食習慣は、虫歯予防の基本です。だらだら食べや飲み物を長時間摂取する習慣は避け、食事やおやつの時間を決めることが大切です。
おやつを選ぶ際は、砂糖が多く含まれるもの(キャンディ、チョコレート、ジュースなど)を控え、虫歯になりにくいものを選びましょう。
・避けるべきおやつ:粘着性の高いお菓子(キャラメル、ソフトキャンディ)、砂糖を多く含む清涼飲料水
・推奨されるおやつ:無糖ヨーグルト、ナッツ類(誤嚥に注意)、野菜スティック、果物(食後に与える)
食後には必ず歯みがきをする習慣をつけ、それが難しい場合は水やお茶で口をゆすぐだけでも効果があります。
2.3-1 小学生の口腔ケア
小学生になると、乳歯から永久歯への生え替わりが本格化し、口腔内の環境が大きく変化します。この時期は、永久歯の虫歯予防と、歯並び・噛み合わせのチェックが重要になります。
2.3-2 永久歯の生え替わりと噛み合わせ
小学校に入学する頃から、乳歯が抜け始め、永久歯が生えてきます。特に6歳頃に生えてくる「6歳臼歯(第一大臼歯)」は、噛み合わせの要となる大切な歯です。この歯は、他の永久歯に比べて虫歯になりやすいため、早期のシーラントやフッ素塗布が推奨されます。
永久歯が生え揃うまでの混合歯列期は、歯並びが一時的に乱れて見えることもありますが、定期的に歯科医院でチェックを受けることで、将来の噛み合わせの問題を早期に発見し、適切な時期に介入することができます。
永久歯は乳歯よりも大きく、溝も深いため、より丁寧な歯みがきが必要です。
2.3-3 歯列矯正の相談の目安
永久歯が生え替わる時期は、歯並びや噛み合わせについて相談する良い機会です。以下のようなサインが見られたら、早めに歯医者に相談してみましょう。
・受け口(下顎前突):下の歯が上の歯より前に出ている
・出っ歯(上顎前突):上の歯が下の歯より大きく前に出ている
・叢生(乱ぐい歯):歯がデコボコに生えている、歯と歯が重なっている
・開咬:奥歯を噛み合わせても前歯が閉じない
・交叉咬合:上下の歯が一部反対に噛み合っている
・乳歯が早く抜けすぎた、またはなかなか抜けない
早期に相談することで、顎の成長を利用した矯正治療が可能となり、将来的な抜歯の可能性を減らしたり、治療期間を短縮したりできる場合があります。
3.通院頻度とスケジュール
お子さんの歯と口の健康を守るためには、定期的な歯科医院への通院が不可欠です。乳歯は永久歯よりも虫歯になりやすく、進行も早いため、家庭でのケアに加えてプロの目によるチェックが非常に重要になります。ここでは、お子さんが健康な口腔環境を維持するための理想的な通院頻度とスケジュールについて詳しく解説します。
3.1 3か月から6か月ごとの定期健診
お子さんの口腔内環境は、成長とともに急速に変化します。3か月から6か月に一度の定期健診が理想的とされています。この頻度で通院する主な理由は以下の通りです。
虫歯の早期発見・早期治療:子供の虫歯は進行が早く、痛みを感じる頃にはかなり進行しているケースも少なくありません。定期健診により、小さな虫歯や虫歯になりそうな兆候を早期に発見し、適切な処置を行うことができます。
口腔衛生状態のチェック:毎日の歯磨きで磨き残しがないか、歯肉の状態はどうかなどをプロの目で確認します。
歯磨き指導と仕上げ磨きのアドバイス: お子さんの成長段階に合わせた正しい歯磨きの方法や、保護者の方が行う仕上げ磨きのコツについて、歯科衛生士から具体的な指導を受けられます。
噛み合わせと歯並びの確認:顎の成長や乳歯から永久歯への生え替わりに合わせて、噛み合わせや歯並びに問題がないかを確認します。必要に応じて、将来的な歯列矯正の相談も可能です。
フッ素塗布の実施:定期健診の際に、虫歯予防効果の高いフッ素塗布を合わせて行うことが一般的です。フッ素は歯質を強化し、酸への抵抗力を高めます。
虫歯リスクが高いお子さんや、歯磨きが苦手なお子さんの場合は、3か月に一度の通院し、お口のトラブルを減らしましょう。
4.受診のサイン
お子さんのお口や歯に異変を感じた時は、速やかに歯科医院を受診することが大切です。特に小さなお子さんは、自分で症状をうまく伝えられないことがあります。保護者の方が日頃からお子さんのお口の状態をよく観察し、以下のようなサインを見逃さないようにしましょう。
4.1 しみる・痛む・口臭が気になるなど
お子さんがこれらの症状を訴えたり、いつもと違う様子が見られたりする場合は、虫歯やその他の口腔疾患のサインかもしれません。
|
サイン |
考えられる原因と対応 |
|---|---|
|
冷たいものや甘いものを嫌がる、しみる |
初期の虫歯や知覚過敏の可能性があります。食事中に特定の歯を避ける、顔をしかめるなどの様子が見られたら注意が必要です。 |
|
歯が痛いと訴える、食事中に痛がる |
虫歯が進行している可能性が高いです。特に夜中に痛みを訴える場合は、神経にまで達していることも考えられます。早急に歯科医院を受診しましょう。 |
|
口臭が気になる |
磨き残しによる歯垢の蓄積、虫歯、歯肉炎、舌苔などが原因となることがあります。一時的なものではなく、継続的に口臭が強い場合は、口腔内の問題が潜んでいる可能性があります。日本歯科医師会でも、子どもの口臭について解説されています。 |
|
歯に食べ物が詰まりやすい |
歯と歯の間に隙間ができている、または虫歯で歯の形が崩れている可能性があります。放置すると虫歯が進行しやすくなります。 |
4.2 歯ぐきの腫れ・出血・白い斑点
歯ぐきの異常や歯の表面の変化は、虫歯や歯肉炎の初期症状であることがあります。早期発見・早期治療が、お子さんの歯の健康を守る上で非常に重要です。
|
サイン |
考えられる原因と対応 |
|---|---|
|
歯ぐきが赤く腫れている、歯磨き時に出血する |
歯肉炎のサインです。磨き残しが原因で歯ぐきに炎症が起きていることが多いです。正しい歯磨き方法を習得し、必要に応じて歯科医院でクリーニングを受けましょう。 |
|
歯の表面に白い斑点や濁りがある |
初期の虫歯(脱灰)のサインである可能性が高いです。歯の表面のエナメル質からミネラルが溶け出している状態ですが、この段階であればフッ素塗布や適切な口腔ケアで再石灰化を促し、進行を食い止めることができます。 |
|
歯ぐきに白いできものがある |
歯根の先に膿が溜まっている「歯根嚢胞」や、歯の萌出に伴う「萌出嚢胞」など、様々な原因が考えられます。自己判断せずに歯科医院を受診しましょう。 |
4.3 転倒・外傷の応急対応
お子さんは活発に動き回るため、転倒やぶつかることによる歯や口の外傷は少なくありません。外傷の程度によっては緊急を要する場合もあるため、冷静かつ迅速な対応が求められます。
|
外傷の種類 |
応急処置と歯科受診の目安 |
|---|---|
|
歯が欠けた、折れた |
欠けた歯の破片があれば、乾燥させないように牛乳や生理食塩水に浸して持参し、速やかに歯科医院を受診しましょう。見た目には変化がなくても、歯の神経にダメージがある可能性もあります。 |
|
歯がグラグラする、位置が変わった |
歯の根や周りの組織にダメージを受けている可能性があります。無理に触らず、早急に歯科医院を受診しましょう。乳歯の場合、永久歯への影響も考慮する必要があります。 |
|
歯が抜け落ちた(脱臼) |
永久歯が完全に抜け落ちた場合、可能であれば1時間以内に元の位置に戻すことで再植できる可能性があります。抜けた歯は、乾燥させないように牛乳や生理食塩水に浸して持参し、すぐに歯科医院へ連絡し受診してください。乳歯の場合は再植しないのが一般的ですが、念のため歯科医院で確認しましょう。 |
|
唇や歯ぐきを切った、出血している |
清潔なガーゼなどで圧迫止血を行い、出血が止まらない場合や傷が深い場合は、歯科医院または口腔外科を受診しましょう。歯への影響がないかも確認が必要です。 |
|
顔面を強く打った |
歯に直接的な外傷がなくても、後から痛みや変色、歯の神経の壊死などが起こる可能性があります。念のため歯科医院で検査を受けることをおすすめします。 |
どのような外傷であっても、お子さんの様子をよく観察し、少しでも異常を感じたら迷わず歯科医院を受診することが大切です。
5.歯医者の選び方
お子様の歯医者選びは、大人のそれとは異なる視点が必要です。一度通い始めると、成長に合わせて長くお世話になる「かかりつけ歯科医」となる可能性が高いため、慎重に選びましょう。特に、お子様が歯医者に対して苦手意識を持たないよう、安心できる環境と信頼できる先生を見つけることが大切です。
5.1 専門性と経験
最も重要なポイントの一つは、専門医や認定医が在籍しているかどうかです。成長段階に合わせた口腔内の発達、虫歯の進行、歯並び、心理状態などを深く理解し、専門的な知識と技術で治療にあたります。
また、お子様の治療経験が豊富な歯科医師やスタッフがいるかも重要です。子供の扱いに慣れているか、優しく声かけをしてくれるかなど、クリニックの雰囲気やスタッフの対応を観察することをおすすめします。
5.2 院内の雰囲気と設備
お子様が歯医者に行くことを楽しみにできるような、子供がリラックスできるような工夫がされているかを確認しましょう。
・診療室の工夫:個室診療など、お子様が怖がらずに治療を受けられるような配慮があるか。
・衛生管理:感染症対策が徹底されているか、清潔感があるか。
・緊急時の対応:AED(自動体外式除細動器)の設置など、万が一の事態に備えた体制があるか。
5.3 治療方針と説明
歯科医院の治療方針が、ご自身の考え方と合致しているかを確認することも大切です。
・予防歯科への注力:虫歯治療だけでなく、予防歯科に力を入れているか。フッ素塗布やシーラント、ブラッシング指導などを積極的に行っているか。
・子供のペースに合わせた治療:無理に治療を進めるのではなく、お子様の気持ちに寄り添い、段階的に治療を進めてくれるか。
・丁寧な説明:治療内容や必要性について、親御様だけでなく、お子様にも分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれるか。疑問や不安にしっかりと耳を傾けてくれるか。
5.1.4 歯医者選びのチェックリスト
お子様にとって最適な歯医者を見つけるために、以下のチェックリストを活用してみてください。
|
項目 |
確認ポイント |
|---|---|
|
専門性 |
専門医や認定医が在籍しているか |
|
スタッフの対応 |
子供の扱いに慣れていて、優しく接してくれるか |
|
院内の雰囲気 |
子供がリラックスできるか |
|
診療室の設備 |
診療台や器具が清潔でキレイなものであるか |
|
治療方針 |
予防歯科に力を入れているか |
|
説明の丁寧さ |
親と子供に分かりやすく、納得できるまで説明してくれるか |
|
衛生管理 |
ゴム手袋・マスクをするなどの感染対策が徹底され、清潔感があるか |
|
アクセス |
自宅や幼稚園・学校から通いやすい立地か |
6.家庭でできる虫歯予防
お子様の虫歯予防は、歯科医院でのケアと、ご家庭での日々のケアの両輪で成り立ちます。特に、乳歯は永久歯に比べて虫歯の進行が早いため、ご家庭での予防が非常に重要です。ここでは、お父さんやお母さんが実践できる具体的な虫歯予防策をご紹介します。
6.1 仕上げみがきのコツ
お子様が自分で歯みがきを始めたとしても、小学校低学年頃までは保護者の方による仕上げみがきが不可欠です。お子様だけでは磨き残しが多く、特に奥歯の溝や歯と歯茎の境目は磨きにくいからです。
仕上げみがきは、お子様の歯が生え始めたらすぐに開始し、乳歯が生え揃い、永久歯への生え替わりが始まる小学校低学年頃までを目安に続けましょう。
・適切な歯ブラシ選び:お子様の口の大きさに合ったヘッドが小さめの歯ブラシを選びましょう。柄が長く、保護者が持ちやすい仕上げみがき専用の歯ブラシもおすすめです。
・磨く姿勢と体勢:お子様を寝かせたり、保護者の膝の上に座らせて頭を固定したりすると、口の中全体が見やすくなり、安全に磨けます。
・力の入れ具合:歯や歯茎を傷つけないよう、鉛筆を持つように軽く握り、小刻みに動かすのがポイントです。ゴシゴシと強く磨く必要はありません。
◆磨き残しやすい場所
・奥歯の溝:食べかすが溜まりやすく、虫歯になりやすい場所です。歯ブラシの毛先を溝にしっかり当てて丁寧に磨きましょう。
・歯と歯茎の境目:歯垢が溜まりやすい部分です。歯ブラシの毛先を歯茎に対して45度くらいの角度で当て、優しくかき出すように磨きます。
・前歯の裏側:見えにくく、磨き残しが多い場所です。歯ブラシを縦にして、一本ずつ丁寧に磨きましょう。
6.2 フロスと歯間ケアの開始時期
歯ブラシだけでは届かない、歯と歯の間の虫歯予防には、デンタルフロスが非常に有効です。歯と歯が接触し始めたら(目安として2歳〜3歳頃から)、フロスを使ったケアを始めましょう。
お子様の歯間ケアには、持ち手が付いていて使いやすいフロスF(ホルダー付きフロス)がおすすめです。保護者の方が安全に、かつ確実に歯間を清掃できます。
・使用方法
1.フロスを歯と歯の間にゆっくりと挿入します。勢いよく入れると歯茎を傷つける可能性があるため注意しましょう。
2.歯の側面に沿わせるようにして、上下に数回動かし、歯垢をかき出します。
3.片方の歯が終わったら、もう片方の歯の側面も同様に清掃します。
4.使用するたびに、清潔な部分を使うか、新しいフロスに交換しましょう。
注意点:歯茎を傷つけないよう、優しく丁寧に行うことが大切です。慣れるまでは保護者の方が行ってください。
7.よくある質問
7.1 子どもが歯医者で泣いてしまうのはなぜ?
お子さんが歯医者で泣いてしまうのは、多くの保護者の方が経験する悩みです。見慣れない場所や器具、初めての経験に対する不安や恐怖が主な原因ですが、適切な対策で乗り越えることができます。
7.1-2 お子さんが泣いてしまう主な理由
・未知への恐怖と不安:初めての環境や見慣れない器具、音に戸惑い、不安を感じます。
・親からの不安の伝播:親が緊張していると、その感情がお子さんに伝わり、不安を増幅させることがあります。
・拘束されることへの抵抗:治療のために口を開けてじっとしていることや、体を抑えられることに抵抗を感じます。
・痛みや不快感への恐怖:過去に痛い経験があったり、痛いことをされるのではないかと想像したりして泣いてしまうことがあります。
7.1-3 保護者ができる対策
お子さんが安心して治療を受けられるように、ご家庭でできる準備と、受診時の工夫があります。
|
対策の種類 |
具体的な内容 |
|---|---|
|
事前の準備 |
絵本や動画で予習:歯医者さんに関する絵本を読んだり、子供向けの動画を見せたりして、歯医者さんが「どんなことをする場所か」をポジティブなイメージで伝えます。 歯医者さんごっこ:お家で歯医者さんごっこをして、口を開ける練習や、歯ブラシを当てる練習をします。 言葉選びに注意:「痛い」「怖い」「注射」といったネガティブな言葉は使わず、「歯を強くしてもらいに行く」「バイキンをやっつけてもらいに行く」など、前向きな言葉で話しかけましょう。 |
|
受診時の夫 |
早めに到着し慣れる:予約時間よりも少し早めに到着し、待合室の雰囲気やスタッフに慣れる時間を作ります。 親が落ち着いて接する:親が笑顔で落ち着いて接することで、お子さんも安心して治療に臨めます。 頑張ったら褒める:治療が終わったら、「よく頑張ったね」「えらかったね」とたくさん褒めてあげることが、次の受診へのモチベーションにつながります。 |
7.2-1 子どもにフッ素は安全性で大丈夫しょうか?
フッ素は虫歯予防に非常に効果的な成分として広く認知されていますが、その安全性について疑問や不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、フッ素の安全性と正しい使い方について解説します。
7.2-2 フッ素とは?
フッ素(フッ化物)は、自然界に広く存在するミネラルの一種で、私たちの身近な食品(お茶、魚介類など)や飲料水にも含まれています。歯の健康を保つ上で重要な役割を果たすことが科学的に証明されており、虫歯予防に有効な成分として世界中で利用されています。
フッ素には主に以下の3つの働きにより、虫歯を予防する効果があります。
・歯質の強化:歯の表面のエナメル質に取り込まれることで、歯を酸に溶けにくい強い歯質に変えます。
・再石灰化の促進:初期の虫歯で溶け始めた歯の表面に、唾液中のカルシウムやリン酸を取り込み、修復(再石灰化)を促進します。
・虫歯菌の活動抑制:虫歯の原因菌の活動を抑制し、酸の生成を抑えることで、虫歯の進行を防ぎます。
7.2-3 フッ素の安全性について
フッ素は、適量を正しく使用すれば安全であることが、多くの研究と実績によって示されています。
・適量での使用:フッ素は、歯磨き粉やフッ素塗布など、用途に応じた濃度と量が定められています。これらの推奨量内であれば、安全性に問題はありません。
・過剰摂取のリスク:非常に大量のフッ素を摂取した場合、歯のフッ素症(歯の表面に白い斑点や縞模様が現れる症状)や、ごく稀に急性中毒を起こす可能性があります。しかし、これは通常のフッ素応用では起こりえないほどの量を一度に摂取した場合に限られます。
・日本の市販品について:日本で市販されているフッ素配合歯磨き粉や、歯科医院で使用されるフッ素製剤は、厚生労働省の承認基準や、日本歯科医師会、日本小児歯科学会などの専門機関が定めるガイドラインに基づき、安全性が確保されています。
フッ素は、虫歯予防のための有効な手段であり、正しい知識と方法で活用すれば、お子さんの歯の健康を守る強力な味方となります。不安な点があれば、かかりつけの歯科医師に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
8.まとめ
赤ちゃんや子供の歯の健康は、乳歯が1本でも生え始めたらすぐに、遅くとも1歳半健診までには歯医者さんデビューを果たすことが大切です。定期的な健診とフッ素塗布、そして毎日の丁寧な仕上げ磨きやフッ素配合歯磨き粉の使用は、虫歯予防の基本となります。早期からの専門的なケアと家庭での実践が、お子様の生涯にわたる健康な歯を守る土台を築きます。お子様が歯医者さんを「怖い場所」ではなく「歯を守る場所」として認識できるよう、親御さんも一緒に前向きに取り組みましょう。
投稿者: