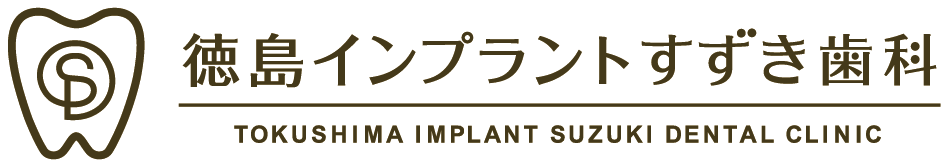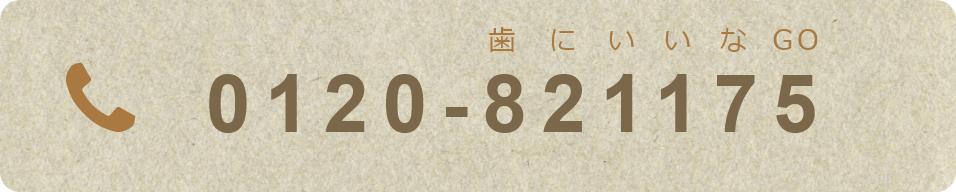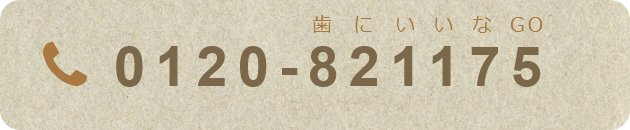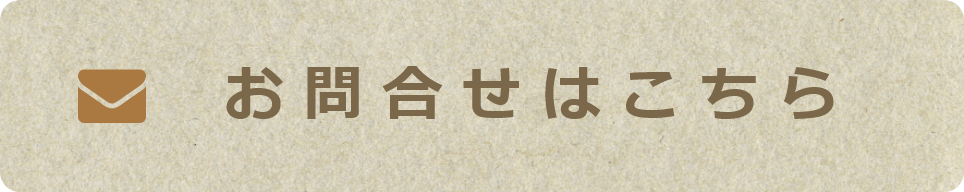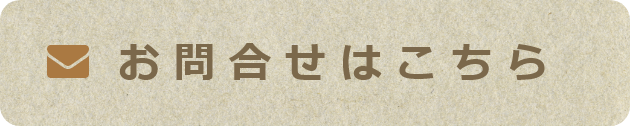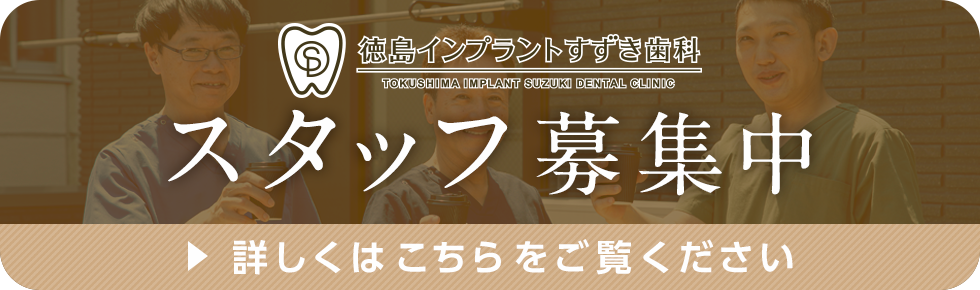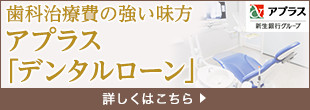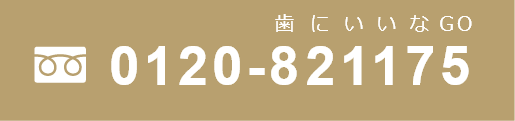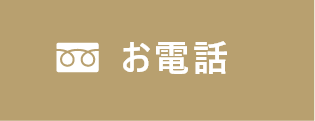- HOME
- 医院ブログ
口腔ケアで誤嚥性肺炎と認知症を予防しましょう
2025.04.11
目次
誤嚥性肺炎とは
食べ物や、飲み物が間違えて気管に入ってしまった時に、コンコンと咳き込んだり、ゴホゴホとむせる事で異物を気管から出す事ができますが、年をとって高齢になると喉の筋肉が衰えます。このむせたり、飲み込んだりする運動が鈍ると、細菌が入った唾液や異物が肺の中に入って、そのまま肺の中で炎症が広がります。これが誤嚥性肺炎です。
また、睡眠中に増殖したお口の細菌を誤嚥することで、誤嚥性肺炎をおこすこともあります。知らないうちに、少量の唾液や胃液が気管に入る不顕性の誤嚥性は本人も自覚がなく誤嚥性肺炎を繰り返しやすくなります。
稀に20~30代の人でも免疫が低下し、体力が落ちていることにより誤嚥性肺炎を起こす可能性がありますが誤嚥性肺炎患者の7割以上が70才を超えていて高齢になるほど感染しやすい事がわかっています。誤嚥性肺炎により、肺に炎症をおこすと、痰に粘り気があり痰の色は濃く、喉にたまってゴロゴロした音が出ます。風邪によく似た症状なので判断がつきにくい場合があります!胸部レントゲン検査で肺炎像があったり、血液検査で炎症反応が大きくなる、白血球が増加するなどがあるときに診断されます。
誤嚥性肺炎、嚥下障害の前兆となる症状には次のような事もあります。
・口の中の食べ物をためてなかなか飲み込まない
・元気がない
・食事でつかれる
・ぼーっとしている
・固形物がかめない。麺など柔らかいものを好む
一見、肺炎の症状とは無関係のような事ですが、高齢者の生活や、行動は注意して見守る事が大切です。
誤嚥には3つの誤嚥のパターンがあります。
嚥下前誤嚥
飲み込むタイミングの遅れや飲み込みの反射が起きないことにより、食べ物や飲み物が気管に落ちこんでしまうことです。
嚥下中誤嚥
飲み込みのタイミングはあっているけど、気管を閉じる力が弱くなっている為、食べ物が押し込まれ気管に入ってしまうことです。
嚥下後誤嚥
物を飲み込む力が弱く、お口の中に食べ物が残って、食道から食べ物、飲み物が溢れて気管にはいることです。
口腔ケアで誤嚥性肺炎を予防できる
◯口腔ケアをしっかりと
歯の表面につく歯垢と呼ばれるバイオフィルムには1mgあたり1億の細菌が存在して、人体で最も高密度な菌の塊がある場所です。バイオフィルムは、お口をゆすぐだけではとれません。バイオフィルムと言う名前の通り、細菌を覆う膜なので、洗口や、消毒液では内部に浸透しにくく、1番に歯ブラシで擦り取る必要があります。特にバイオフィルムが残りやすい、歯の裏側や歯の生え際を歯ブラシでしっかり落とし、歯ブラシでは届きにくい歯と歯の間はデンタルフロスや、歯間ブラシを併用しましょう!口腔ケアをしっかり行う事で、細菌を減らせば万が一誤嚥しても肺炎を発症する確率は減ります。
◯唾液の分泌を促す
唾液には天然の抗菌作用があり、他にも粘膜保護作用があります。唾液分泌を促す方法として、唾液腺マッサージがあり、耳下腺、顎下腺、舌下腺をマッサージしましょう!
食べない事は唾液が分泌しないので、なるべく経口摂取するようにしましょう。また人はリラックスする事により、副交感神経が働き、耳下腺からサラサラの唾液が分泌されやすくなります。
◯全身の脱水に気をつけましょう
こまめに水分補給をしてお口の潤いを保つのも大切です。口腔乾燥すると痰が口腔粘膜の剥離にからみ、粘膜について取れにくくなります。
口腔ケアをする時に保湿ジェルを万遍なく付けて潤いを保ちましょう。
◯舌苔の取り過ぎに注意しましょう
舌につく白い汚れを舌苔と言います。
舌苔が、うすくついている事は正常です。過度に取ると味蕾という、味を感じる場所が傷つけてしまうので舌苔を取る時はスポンジブラシを濡らし軽く湿らせる程度の水分で拭い取るのがおすすめです。
◯歯科医院で歯の定期検診をうける
歯磨きだけでは落ちない場所の汚れや歯石をとりバイオフィルムがつきにくい環境作りをしましょう!歯と歯茎の伱間にできる歯周ポケットの汚れは歯ブラシでは落とせません。専門の器具を使い歯周病を予防しましょう。
◯入れ歯の洗浄と調整をしましょう
入れ歯を入れている人は入れ歯無しの人に比べて誤嚥性肺炎のリスクが高くなります。また入れ歯を毎日洗浄する人としない人では誤嚥性肺炎を発症する確率が1.3〜1.5倍洗浄しない人が高くなっています。入れ歯にもバイオフィルムや歯石までつきます。入れ歯用の義歯ブラシで入れ歯を磨きましょう。入れ歯の金属のバネの部分は特に汚れがつきやすく、また残りやすい場所です。
夜間寝る時は外して、洗浄液につけましょう。その時大事なのは、洗浄液につける前に、ブラシで水洗いをしてから洗浄液につけることです。
お口の中から出した入れ歯を洗わずそのまま洗浄液につけても効果はありません。必ずブラシで水洗いしてから洗浄液につけましょう。
ご自身の歯が残っている人はバネが引っかかる歯が特に汚れが残る場所ですので、しっかり歯ブラシで磨きましょう。
認知症を予防しましょう
認知症とは色々な病気が原因で記憶や物事を考えたり、判断したりという認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす症状が出る事です。認知症の最大の原因は加齢であり、大きく分けて4つの種類の認知症に分けられます!
◯アルツハイマー型認知症
日本人で最も多い認知症です。脳の神経細胞にタンパク質が溜まり脳が萎縮する病気で、加齢や遺伝による原因も考えられますが、はっきりしていません。
しかし、糖尿病や高血圧の人はアルツハイマー型認知症になりやすい事がわかっています。初期段階で治療を始めれば進行スピードを遅らせる事ができます。
◯ルビー小体型認知症
ルビー小体という特殊なタンパク質が脳に溜まり細胞が壊れることで発症する原因不明な認知症です。男性の発症率が高い認知症です。
◯血管性認知症
脳出血、脳梗塞、くも膜下出血という脳卒中で、脳の神経細胞を圧迫したり、血流が悪くなったり酸素や栄養を送れなくなることが原因で発症します。損傷した脳の場所により症状がかわり、症状の波があることから、まだら認知症と呼ばれることもあります!ストレスや生活習慣が原因となるので、生活習慣の改善が必要です。
◯前頭側頭型認知症
脳の4割にあたる、前頭葉と側頭葉が萎縮して血流が悪くなり発症する認知症です。症状としては、人格の変化や異常行動があり、精神疾患とよく間違われる認知症です。
認知症を予防する為には
・バランスのとれた食事で、青魚や大豆、卵や、緑黄色野菜をしっかりとりましょう。
・適度な運動をしましょう運動する人としない人を比べると運動する人の方が認知症を発症しにくいです。
・コミュニケーションをとりましょう話をするだけでも、脳が刺激され生活にもメリハリがでて、自然に行動をおこしたり、楽しい気分になります。
・口腔ケアをしましょう
歯磨きと口腔ケアは違います。歯磨きとは、歯を磨くことであり口腔ケアとは歯の有無に関係なく、入れ歯のお手入れや管理をしたり、口腔周囲筋のマッサージや、嚥下、咀嚼のトレーニング、舌苔やバイオフィルムを取り除くなど、お口全体のケアをすることです。
まとめ
誤嚥性肺炎や認知症は高齢者に発症しやすい病気ですが、若い人の誤嚥性肺炎、若年性認知症もあります!
口腔内が不潔になれば、細菌が血流にのって全身に運ばれ全身に悪影響を及ぼし、認知症や、誤嚥性肺炎だけでなく、糖尿病や心筋梗塞のリスクも上がります。しかし、口腔ケアにより、唾液分泌が多くなることで、自然の自浄作用で細菌を流す事や、咀嚼、嚥下トレーニングをしたり、定期的な歯科検診を受けて歯ブラシだけでは落ちない場所の細菌を落とし、しっかり噛めるようにすることで、全身の健康につながります!お口の中をスッキリさせて、健康を維持していきましょう。
投稿者: